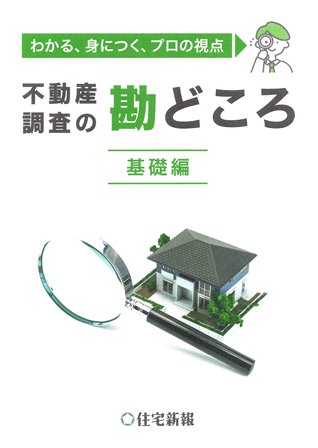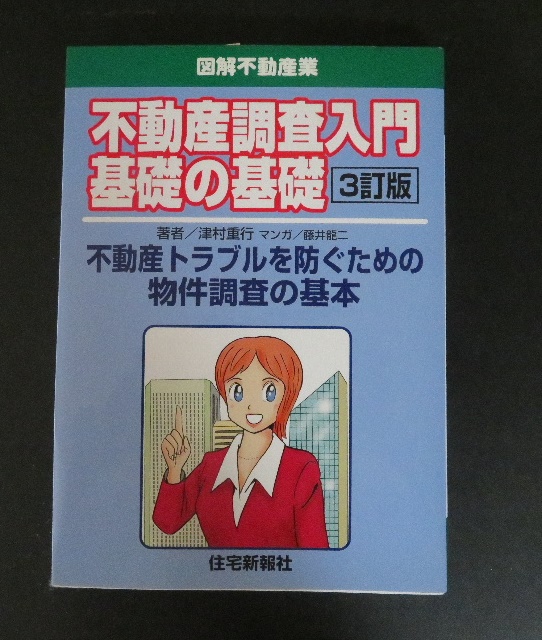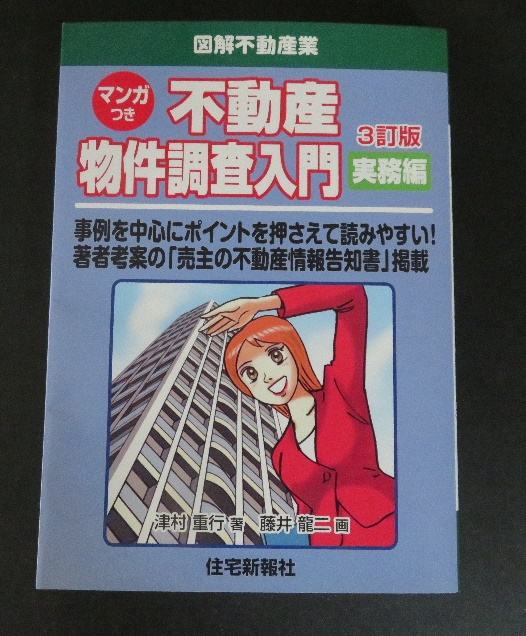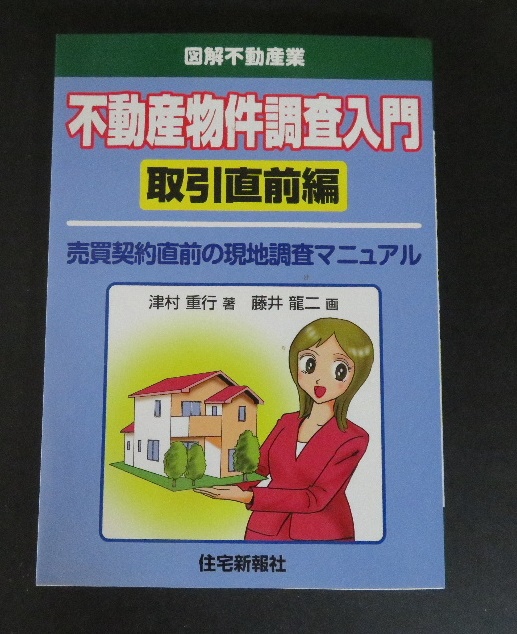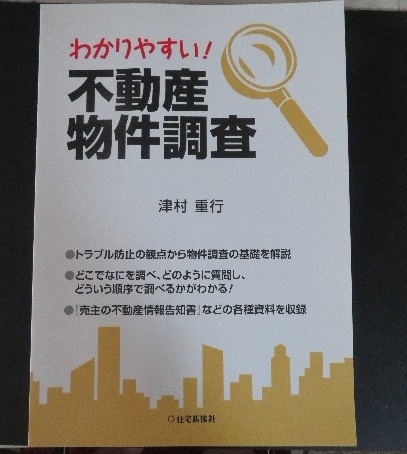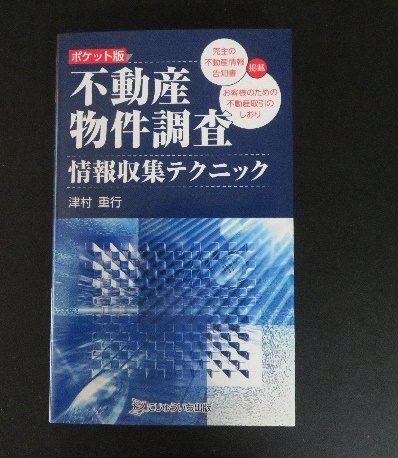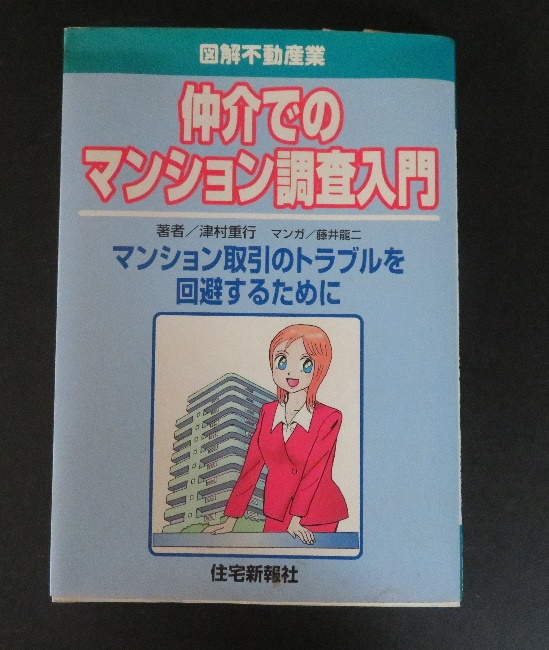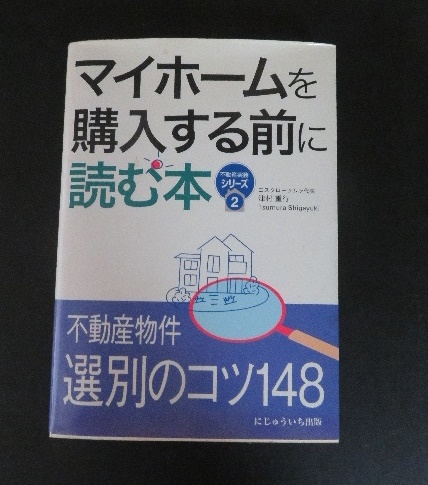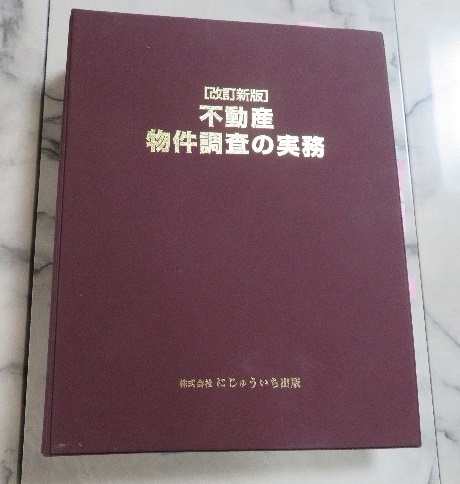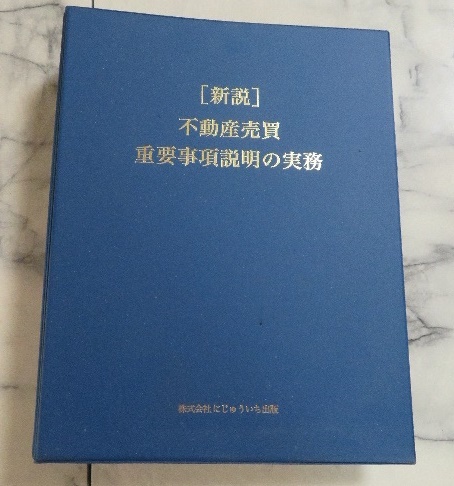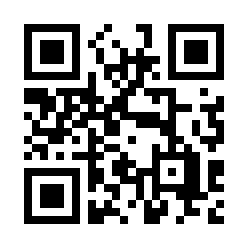2025年4月1日施行の改正建築基準法をめぐって、不動産流通業界では、その対策が急がれています。
いくつかの意見が出ていますが、その中で、特徴的になっていることを紹介したいと思います。
最初に問題になるのは、新築の際の問題でしょう。
確認が必要な建築物において、4号建築物が廃止され、2号と3号に分割されたことですね。
審査対象外にしていた建築物の範囲を縮小して、木造平家建物で200㎡以下だけが
確認の審査対象から外れました。
我々は中古住宅の不動産取引を前提として研究をしている立場のため、新築工事は、建築会社にお任せしましょう。
本章で、問題になるのは、中古住宅の仲介で、新しい建築基準法がどのように影響するか?という点です。
一言でいえば、買主が、現在の中古住宅を購入するにあたり、増改築をすることを訴えて、売買契約をする人の場合、不動産仲介の注意点は何か、ということです。
売買契約の特約では、以下のような手法があります。
「1.本件建物は改正建築基準法第6条第1項第2号に該当し、審査省略制度の対象外となるため、本件建物を増改築を行う場合、必要図書が存在しないことにより、増改築等の実施が困難となる、または制限を受ける可能性があります。さらに、建築確認の申請が可能であっても、必要図書の作成が求められることにより、工事費用の増加や工期の遅延が生じるおそれがあります。
2。 買主は、上記の内容を理解し、これを容認するとともに、この点に関して売主に対して契約不適合責任を追及しないことを確認しました。」
確かに、この方法は、順当な特約といえるでしょう。
しかし、買主は、あらかじめ、増改築をしたいので、これを前提に売買契約をするといっているのだから、買主の契約内容は、「増改築ができること」です。
そうすると、上記特約は、最初から、「買主の契約内容は、契約内容不適合には該当しない」と、あり得ない特約になっています。
買主は、増改築できると思うから売買契約するのであって、できないとわかっていたら、最初から契約しないでしょう。
このような特約をしていると、「本件特約は、有効ではない」と、判断されかねないですね。仲介業者にも、その責任を問われるかもしれません。
これは、増改築できない場合でも、不適合として、売主には損害賠償請求をしないでくれ、というのですから。
私が考えた特約(案)は以下のとおりです。
未だ、考え付いたところで、今後、改訂する可能性が高いです。
「買主は、本物件建物において、増改築工事を予定していますが、2025年4月1日施行の改正建築基準法により、確認申請の際、建築基準関係規定に適合することを証明する書類の提出が義務付けられており、万一、確認済証が交付されない場合は、本契約を白紙解除とする。ただし、建築関係規定等の図書や省エネ関連の図書の提出が追加で必要となった場合の書類作成費用は、買主の負担する。」
こんな感じで作成してみました。
通常の木造2階建て、120㎡位の木造建築物の売買ですと、「既存建物の仕様表」の提出が、増改築工事の際に必要になりました。
このような図書がない建築物が多いですね。
場合によっては、「この書類がないために、増改築ができなかった」という苦情の対策が必要になります。
建築士によれば、費用がかかるが、この仕様表を作成することができるようです。
法改正後の建築基準関係規定に適合することを証明する図書は、「構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書」が追加になりました。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」